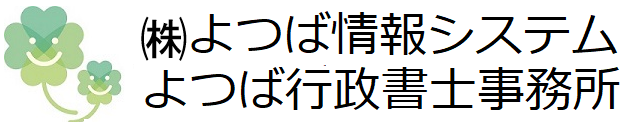システム開発費はどうやって決まるのでしょうか
今回は非常にセンシティブな内容のため従来より増して私見としてお読み頂けると幸いです。
まず結論から言ってしまうと「言い値」です。
言い値と表現すると「ぼったくり」と捉える方も多いでしょうがこの場合の言い値とは「価格を付けるのが非常に難しいもの」という風にご理解下さい。
物の値段はそれにかかったコストに利益がプラスされて決まります。
ではシステム開発のコストとは何でしょうか。
1.システムの仕様を決めるための検討時間
2.実際にシステムを開発する時間
3.システムが正しく動作するか検証する時間
大きく分けるとこの3つです。
このうちお客様が「原価」として理解されるのは2です。
そこには材料費などはかからず家賃などの運営費と人件費「だけ」なので「高い」と思われるのかも知れません。
しかしシステムを構築するという事は、まず現業フローの何が問題でどのようなシステムを構築すべきかという1.システム検討のフェーズが開発の中で最も重要となり、この部分を丁寧に構築しないと大抵トラブルになります。
具体的には以下の流れになります。
・現状の業務内容を口頭説明、紙の資料、現状運用中のシステムから推測する。
・お客様が何を求めているか、どこに改善点があるかを具体的にご提示します。
・またお客様自身が気付いていない点をご提案します(ちなみにここで腕の差が出ると私は考えます)。
・その上でコスト見合いなど様々な条件を勘案した上でベストな落としどころを探ります。
2でベンダーは粛々と作り上げます。
3のテストフェーズもお客様のご協力次第でシステムが良い物になるかトラブルの元となるかが変わってきます。
「作った側がきちんと動く物を作るのは当たり前だ」それはごもっともです。
しかし仕様通り作ったとしてもいざ動かしてみたら「イメージしたのと違う」という事は往々にして起こります。
これがスクラッチ開発におけるトラブルのあるあるであり、ここから「言った言わない」の泥沼が始まるのです。
せっかくご縁がありよつばにご依頼頂いたのにそのような結果になってしまっては双方にとって不幸です。
なのでよつばはお客様がどれだけ新しいシステムを必要としているかの「熱意」を見させていただく事にしているのです。
熱意とはお金の事ではありません、前述1と3にどれだけご参加頂けるかという事です。
それに我々は品質をもって応えたいと思っています。
話を言い値に戻します。
このような数値化しにくい物に値段を付けるにあたってベンダー側としては「工数(日数)」✕「単価」で表現します。
そこにはエンジニア個人の資質や能力は加味されませんし、結局は根拠が必要なので仕方なく鉛筆を舐めて提示している訳です。
そういう意味では壺とか絵画に近いです、あちらは芸術品なので価値が解る方が納得すれば契約が成立しますがシステムは実用品という点が余計問題をややこしくしているのかも知れませんね。
最後に社内システムを導入したから何人削減したという話は正直聞いた事がありませんし、そのような観点でシステム導入しようとすると現場の反発を招き大概失敗します。
それよりもシステムを導入する事により得られる下記のメリットをよくご検討された上でベンダーから提示される金額と比較し導入の可否を決めて頂くのが良いかと思います。
・どれだけ業務が軽くなるのか
・どれだけ業務速度が上がるのか
・どれだけ業務の継承が楽になるのか
・どれだけデータ不一致などのリスク軽減されるのか
言い換えると「お客様がそのシステムにいくらの価値を付けるか」ではないでしょうか。
よつばでは新規システム構築のサポート及び構築のご相談をお受けいたします。
お支払いについても高額な初期コスト負担ではなく、月額保守料に分割するなどの負担の少ない形での導入もご用意しております。
【今回の補足】
・センシティブな内容 : ベンダーとしては一番触れてほしくない「周知の事実」
・システム屋の腕の差 : 改めて記事にするつもりですが、昔から「言われた事だけシステム化するSEはヘボ」と言われ、お客様が気付いていないリスクやシステム的な拡がりを指摘し提案できるかどうか、それを具現化できるかどうかが腕のいいSEとなると私は思います。
・単価 : ちなみに大手ベンダーの最近(2023年)の単価は約7万円/日くらいです
・鉛筆を舐める : 古臭い表現ですが「フィクションを書く」という意味でしょうか